BTS、グラミー賞なるか? K-POP隆盛から思い描くJ-POPの将来像

4月4日(日本時間)に米ラスベガスで授賞式が行われる第64回グラミー賞の「Best Pop Duo/Group Performance」部門で、BTSの〈Butter〉がノミネートされた。BTSは昨年のグラミー同部門でも〈Dynamite〉でK-POPアクト史上初のノミネートを達成。その快挙は、「ARMY」と呼ばれるファンダム(熱心なファン)の枠組みを超えて祝福された。〈Dynamite〉は惜しくも受賞を逃していただけに、次の一手も注目を集めた。2021年のBTSは、〈Butter〉以外にも、エド・シーランが作曲に参加した〈Permission to Dance〉、コールドプレイとのコラボレーション曲〈My Universe〉の3曲でビルボードHot100チャートの1位を獲得し、年間で最多のナンバーワン・ヒットを記録。これもアジア系アーティストとしては初の偉業である。(忠聡太・福岡女学院大学講師)
K-POPの成功の陰に…
ひるがえって、J-POPの海外での存在感はどうだろうか。少なくともアメリカでのアワードやチャートでの実績に関しては、K-POPと比較するレベルにも達していない。J-POPに限らず、日本の文化を愛好するファンが世界各国に存在していることは確かだが、その人気は各地域での主流メディアに食い込むほどではないだろう。
世界各地の日本文化人気をささやかな火種とするならば、いわゆる「クール・ジャパン」政策は、それらが放つ小さくも強い光をクローズアップして日本に伝えるばかりで、さらなる燃料となる制作への支援や、新しいメディアを駆使して火と火をつないでいくことには消極的だった。とくに新しいプラットフォームへのシフトに関しては致命的に後れを取り、今や最も重要な音楽メディアとなったYouTubeには公式のMV(ミュージック・ビデオ)が一部しかアップされず、しかも海外からはアクセスできない状況が長らく続いていた。
皮肉にも、インターネット以降の海外におけるJ-POP熱を支えていたのは、そうしたバリアーを破って違法アップロードされた動画や音源である。そのなかでも、J-POPはアニメやドラマと共に流れるものとして親しまれていた。NHKワールドTVが国際的に放送している音楽番組「J-MELO」が2010年前後に行った視聴者調査では、90年代以前にはテレビで、2000年代以降にはインターネットで、日本のアニメと出会ったことをきっかけに音楽にのめりこんでいったファンが視聴者の多数派を占めていた。

こうしたアニメのグローバルかつイリーガルなファンダムは、スマートフォンの普及と共にすっかり主流となった、映像ありきの音楽体験を先取りしていたと言えるだろう。やがて、その動向は日本国内での流通を前提につくられる番組や音盤を軸とするJ-POPではなく、全世界で一斉公開されるYouTube上の映像を中心に動くK-POPの支持へと収斂(しゅうれん)していく。
同一線上でつながったアニメとK-POP
実際に、もともと日本のアニメを愛好していた層が、その延長線上でK-POPにハマっていく傾向があることもしばしば指摘される。楽曲に合わせて目まぐるしく移り変わるセットと、そこで躍動するアイドルたちに目を喜ばせ、その中からとっておきの一人を「ペン」や「推し」として選び、愛を注いでいく傾向は、多数のキャラクターが行き交うアニメとそのグッズ展開の構造に類似しているだろう。
また、入念にコンセプトが練られたMVには、その世界観や設定の奥行きをほのめかす要素が高密度でちりばめられ、ファンはそこに秘められたメッセージや、他のMVとの関連性を熱心に読み解くことに余念がない。こうした考察欲求を刺激する映像づくりにも、アニメのファン文化との親和性が認められる。
もちろん「推し」ベースの楽しみは日本のアイドル文化にも広く見られるが、海外に向けたYouTube上でのMV公開はそれほど重要視されていなかった。ジャニーズ系タレントのMVは、ドメスティックに流通するCDの購入特典であるDVDを入手しないかぎりは全編を視聴できない。「AKB商法」とやゆされる仕組みも、ウェブ以前のメディアであるCDの購入やテレビの露出と結びつき、そのゴールは日本国内での露出だった。一方、K-POPはYouTube上でのMV公開を基軸としたリリースを展開し、再生回数の増加はそのまま世界的なプレゼンスの向上にはねかえる。

映像と音楽とキャラクター性を密接に結びつける文化は日韓のみに見られるものではないが、こうしたつながりからは「プロ意識が強いK-POP」対「不完全さをめでるJ-POP」といった、国ごとの「らしさ」を強調する議論からは見えてこない論点が浮かび上がってくる。先述した「J-MELO」の調査には、東方神起の日本語バージョン楽曲をきっかけにJ-POPにのめりこんだというファンの声も寄せられており、おそらく日本人が思っている以上に非東アジア圏におけるKとJの境界は曖昧である。K-POPの国際的な躍進をきっかけとして、国境による区別を前提とせず、東アジア圏あるいは環太平洋圏で広く共有できる新たな文脈を掘り起こすこともできるだろう。
そこで重要な課題となるのが、20世紀以降の東アジア諸国とアメリカ文化の関係性をめぐる歴史の再考である。『動物化するポストモダン』で東浩紀が主張したように、アニメに代表されるオタク文化を国民的な現象として祭り上げる動きは、その母体となるSFや特撮といったサブカルチャーの根底にあるアメリカからの絶大な影響を見えにくくした。日本の音楽文化においても同様の傾向は見られる。故・大瀧詠一は、アメリカも含む世界各国の音楽を土台として急造された明治期以降の日本の音楽を、「分母」たる世界史の上に置かれた「分子」として捉えた。さらに大瀧は、この「分子」を土台として模範する音楽の登場が引き起こす「分母」の忘却、つまり本来は海外の様式なしには成立しえない「J-POP」を純日本的なものとみなす動きが起こることを予見していた。

こうした近視眼的な自国礼賛の結果として「クール・ジャパン」が不発に終わったことを念頭に置きつつ、話をBTSに戻そう。彼らが初のグラミー・ノミネートを獲得した〈Dynamite〉と、それに続く〈Butter〉や〈Permission Dance〉は、アメリカの音楽とダンス文化の影響力を再確認する試みとしても捉えられる。とくに70年代以降のディスコ文化への憧憬(しょうけい)や、歌詞で明示されるMTV時代最大のスターであるマイケル・ジャクソンへのリスペクトは注目に値する。ソロ・デビュー後のマイケル・ジャクソンの功績のひとつは、白人優位が圧倒的だったMTV黎明(れいめい)期に、人種的な多様性をもたらしたことだった。BTSが初の全編英語詞曲である〈Dynamite〉で勝負に出るに当たって、ディスコ的な美意識を全面的に押し出したのは、流行のレトロ志向を表面的に取り入れるためではなく、新たな映像メディアを駆使して既存のシステムに挑んだ先人の神話に、自分たちの来し方と行く末を重ねようとしたが故であるように思われる。そんなマイケル・ジャクソンも、ソロ名義でのファースト・アルバム『Off The Wall』はグラミーで冷遇され、その雪辱を続く『Thriller』のグラミー8部門制覇で果たしている。
のろしはジャニーズから?
K-POPの成功に刺激されて、日本でも次第にグローバルな展開に向けた動きと歴史の編み直しは進んでいる。たとえば、K-POP史をまとめた書籍の相次ぐ刊行によって、マイケル・ジャクソンゆかりの振付師を迎えて研さんを積んだジャニーズ史上屈指の実力派である少年隊が韓国の音楽界に与えた衝撃が明らかになり、YouTubeにアップされた過去の映像と共にその再評価が進んでいる。

こうした動きを受けて、ジャニーズ事務所の若手ユニットであるTravis Japanは、2021年から「+81 Dance Studio」と名付けたシリーズを展開。やはりマイケル・ジャクソン『THIS IS IT』の振付師であるトラヴィス・ペインの薫陶を受けて名付けられた彼らは、技巧のK-POP/稚拙なJ-POPという単純な図式を打ち崩すには十分過ぎるほどのダンス技術を誇る。「+81 Dance Studio」では、海外でもすでに広く定着しているアジア系ダンス・コレクティヴが発信する動画のフォーマットを意識した構成で、歴代ジャニーズのさまざまな楽曲を先鋭的で高度な振り付けと併せて掘り起こし、「ジャニーズ系」あるいは「J-POP」とひとくくりにするにはもったいないほどの音楽的なバラエティー性とポテンシャルを世界に向けて発信した。さらにTravis Japanは、2022年春以降にロサンゼルスに長期滞在して世界を目指すことを発表し、かつてBTSがリアリティー番組『防弾少年団のアメリカンハッスルライフ』でたどった道のりをなぞるかのような軌道を描きはじめた。
そもそも、カリフォルニア州出身のアジア系アメリカ人である故・ジャニー喜多川が芸能事務所を設立した背景にはアジア太平洋戦争と朝鮮戦争以降の冷戦があり、そうしたコンテクストをたどりなおすフィクションが近年人気を博していることも興味深い。たとえば韓国では、カン・ヒョンチョル監督による映画『スウィング・キッズ』や、イ・ジンによる小説『ギター・ブギー・シャッフル』など、1970~80年代生まれの比較的若い世代の目線で朝鮮戦争前後の米軍基地と音楽文化の関係性を捉えなおした作品がヒットしている。日本でもNHKの連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』の第一部で、ジャズと野球を軸として戦前から占領期のアメリカ文化受容が描かれた。また、アメリカでは映画『ウエスト・サイド・ストーリー』のスティーヴン・スピルバーグ監督によるリメーク版が2021年に公開されている。本作は直接的にアジア系移民を取り上げたわけではないが、20世紀中葉の冷戦期アメリカにおける移民と音楽とダンスの関わりをダイナミックにとらえたこの物語が、ジャニー喜多川を初代ジャニーズ結成へと駆り立てたことはよく知られている。

BTS悲願のグラミー受賞をめぐってますます高まっているK-POPの国際市場でのプレゼンスは、アメリカのはるか西で展開したいくつもの複雑な物語をどうよみがえらせていくのだろうか。
◇ ◇ ◇
忠 聡太(ちゅう・そうた)1987年生まれ、栃木県出身。日本学術振興会特別研究員などを経て、2016年4月から現職。専門は近現代文化史、ポピュラー音楽研究など。主な書籍に毛利嘉孝編著「アフターミュージッキング―実践する音楽―」(東京藝術大学出版会)、南田勝也編著「私たちは洋楽とどう向き合ってきたのか─日本ポピュラー音楽の洋楽受容史」(花伝社)など。
(2022年3月24日掲載)
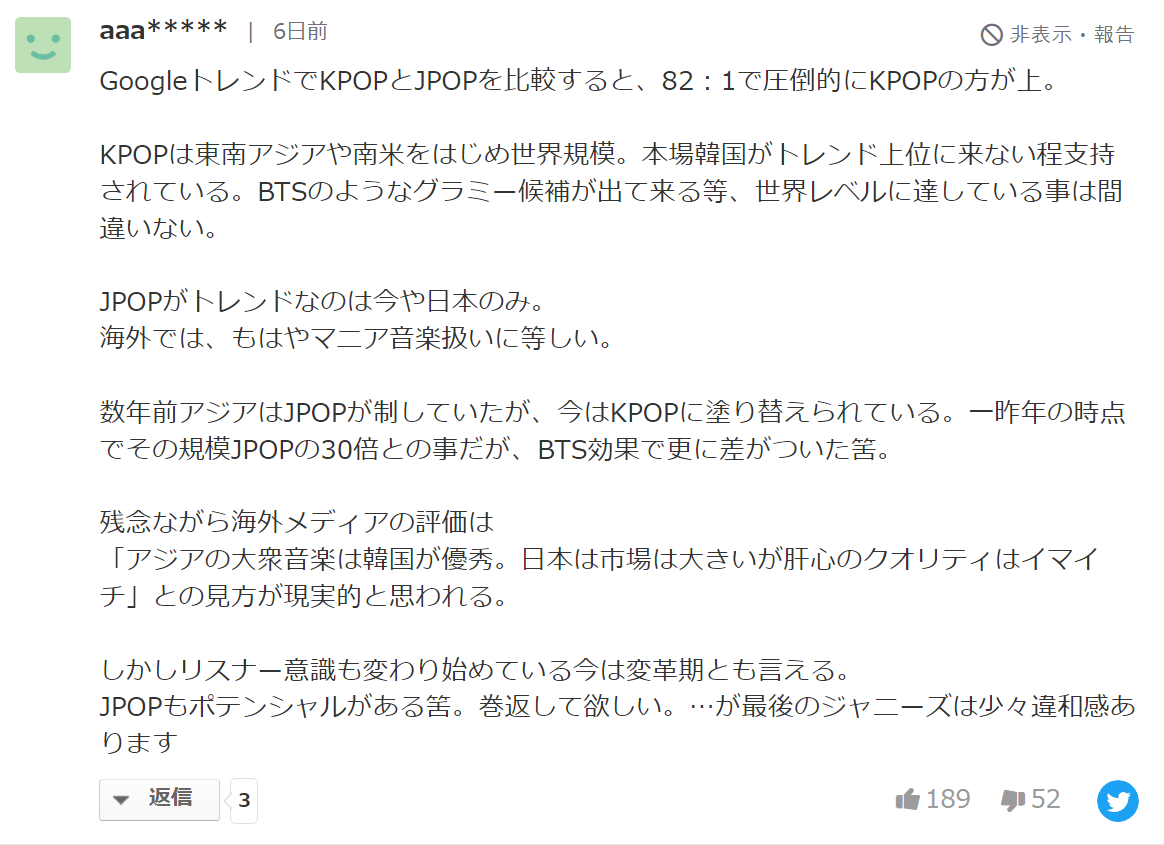
'Japanese Nationalism > Text' 카테고리의 다른 글
| ジャニーズは「歌もダンスも素人みたいなもん」 (0) | 2022.04.07 |
|---|---|
| ペトロナスツインタワーの設計を日本から捏造するネット右翼 (0) | 2022.04.07 |
| 日本性犯罪統計の真実 (3) | 2022.03.31 |
| 試し腹から捏造するネット右翼 (0) | 2022.03.31 |
| パラオの橋で捏造するネット右翼 (0) | 2022.03.26 |


